【書評・要約】シリコンバレー式 超 ライフハック 読みました。
デイヴ・アスブリーさんの書かれた、シリコンバレー式 超 ライフハック読みました。
そして、要点をまとめてみました。
デイヴ・アスブリーさんは、シリコンバレーのテクノロジー起業家で、成功するも肥満と体調不良になってしまうのですが、大量の金額を投じて、心身の能力を向上させる方法を研究し、50キロ痩せることができました。
そのノウハウが、取り上げられて、多くのメディアで話題となったようです。
本書では、450名の著名な成功者にインタビューを行った結果、浮かび上がってきた成功の秘訣を42のハックとして、紹介されています。
一人ひとりの専門家がそれに注いだ時間を足し合わせれば数十万時間にも上る研究、実験、そしてそれらの結果の集大成だ。
もっと、自分の能力をあげていきたい、人生をよくしていきたい方、一緒に読んでいきましょう!

もっと賢く、もっと速く、もっと楽しくなりましょう!
シリコンバレー式超ライフハック の 目次は、こちら ↓
はじめに——「人類史上最強の技」を全部伝授する
■PART1:もっと賢く SMARTER
第1章:自己——「新しい自分」を脳にしみこませる
第2章:脳——習慣とトレーニングで強化する
第3章:恐怖——邪魔な原始的本能をリセットする
第4章:休息——自分を「アップグレード」する時間をつくる■PART2:もっと速く FASTER
第5章:快楽——意識の変容に至る究極の秘法
第6章:睡眠——努力しなくてもできるライフハック
第7章:運動——「間違いだらけの運動」をいますぐやめよ
第8章:食事——身体が変わる「おばあちゃんの最強の教え」
第9章:テクノロジー——とうに「未来」は到来していた!■PART3:もっと幸せに HAPPIER
第10章:幸福——お金で買えないなら、何で買える?
第11章:人間関係——「だれとつながるか」で人生の多くが決まる
第12章:瞑想——非常識思考の街の「新しい常識」
第13章:自然——大人も「泥遊び」をすべき科学的理由
第14章:感謝——この章だけ読んでも効くほど強力なハック
意志力
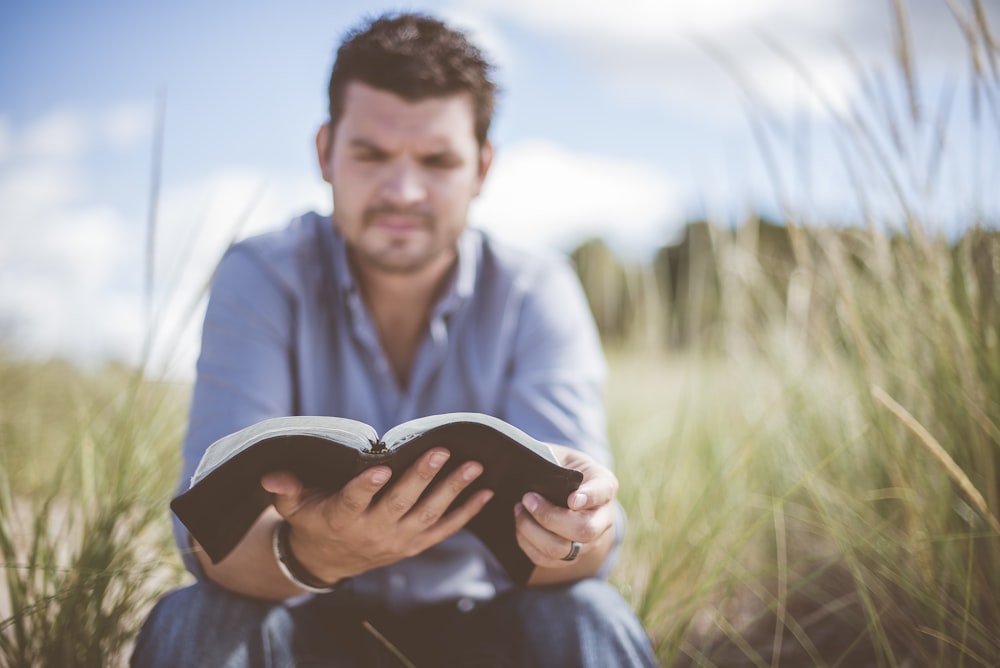
まず、自分の大事なことに、集中することが大事です。
そして、脳には、限界があるので、しっかり管理する必要があるようです。
そのために、20年後の理想的な自分を思い浮かべましょう。
あなたの2040年の「ある一日」は、どんな一日だろうか?
長期的な理想を明確にすることで、大事なことが見えてきます。
朝起きてから、SNSをチェックして、返信をして、一日にどれくらいの意思決定を行っているでしょうか?
人が、意思決定できる量には、限りがあるようです。
裁判官の判定は、なんと 午前と午後で変わってしまうようです!
意志力は、筋力のようなもので疲れてしまうと、力が発揮できないのです。
意志力は、負荷をかけて強化できます。
著者は、握力グリップを握りつづけたり、息を限界までとめるトレーニングをしているようですw
また、意思決定の数を減らすために、ルールを作って、意思決定の数を減らすのも効果的とのこと。
方法の一つとして、ジョブスが、毎日黒いタートルネックを着ていたように、”何を着るかで悩むのをやめようましょう。” と言われています。
人は、興味あることには、集中できるしモチベーションも高まりますが、興味ないことには、力が出せません。
専門家によると、興味ないことは、興味ある事の10分の1しか吸収できないようです。
「エネルギーを失わせること」をしないで、「関心はないが重要で有効なこと」と「やる気と喜びを与えてくれること」を10:90 でできると理想的なようです。
エネルギーを失わせることばっかりやってます。。
完全にやらないことは、できないので、エネルギーを失わせることが、喜びを与えてくれるように、方法を変えればよいかもしれません。

興味ある方にシフトできるように、見直します!
言葉の力

著者の親友で、健康増進のエキスパートである J.J.ヴァージンさんは、息子が事故にあってしまいました。
そこで、治療にあたっていた医者が、「もし息子さんの意識が回復すれば、歩けるように最善を尽くして治療にあたります」と言ったので、追い出してしまったそうです。
少しでも、回復できないと思わせたくなかったそうで、実際、J.Jさんのおかげで、息子のグランドは、回復できて当然だと思え、回復していけたとのことです!
「絶対に成功を呼ぶ25の法則」の著書 ジャック・キャンフィールドさん のオフィスには、NGワードがあって、それを言うと2ドル払うルールのようです。
それは、罰金ではなく、マイナスな言葉が、2ドルのコストを生じさせることを体感するためとのことです。
・できない(CANNOT) - 100%うその言葉
・必要がある(NEED) - ささいなことを重大事と勘違いさせる言葉
・悪い(BAD) - 解決の可能性を閉ざす言葉
・やってみる(TRY) - やるつもりがないことが織り込まれた言葉
ここは、日本語と英語の表現で、理解するのが難しいところがありそうです。
“できない“ は、理解できますが、”必要がある“ というのは、普通に使いそうです。
“必要がある” の代わりに、ささいなことを重大事と勘違いさせる言葉だと 「するべきだ」、「こうあるべきだ」、「~でないとだめだ」、「当然~だ」 などでしょうか。
納得できないないようでも、こういう言葉で、言われると 周りも考えてしまいそうです。
“悪い“ も どうにもならない とか どうしようもない などのニュアンスが入っていそうです。
どうしようもない は、ネガティブで、解決できない感じなので、使わないようにしようと思いました。
“やってみよう“ は、いい言葉だと僕は、思います。
なんでも、よさそうであれば、やってみることは、成長にもつながると思います。
しかし、見方によっては、できないかもしれない というニュアンスは含まれてますね。
アップグレード

20世紀にはいって、「神経可塑性」という概念が理解されだしたようです。
人間は、生涯にわたって新しい細胞を成長させ、新しい神経結合を形成する という考え方だ。
歳は関係ないのですね!
ただし、行動を習慣化して、意識できなくてもいいようにするには、ニューラルネットワークを形成する必要があるので、努力が必要です。
私たちは、思い込んでること(本書では信念)で、現実を見ているが、信念は、現実ではないと 言われています。
信念は、古いハードウェアなので、アップグレードもできるし、交換も可能なようです。
大事なプレゼンの前に縁起の良いことがあったから、プレゼンは絶対成功すると確信している人がいるとする。ここで、そんな因果関係が実際に存在するかどうかは問題ではない。その存在を信じることで自信を強めた人は実際に立派なプレゼンをやってのけるだろう。

ネガティブな信念は、捨てて、ポジティブな信念にしていきましょう!
本を読むのは、効率のよい学習の一つとして紹介されていました。
著者が数十年かけて蓄積した経験と知恵を注ぎ込んだ一冊の本を一日とか二日で読んで、その内容を取り込めるからです!
確かに!
本を読む効率よく吸収するコツ FAST
・FORGET(忘れる)
これから本を読んで吸収しようとすること以外、全て忘れる
・ACTIVE(能動的)
積極的に、ノートを取り、学んだことを共有する。
・STATE(状態)
脳と体の状態を整える。
・TEACH(教える)
人に教えるつもりで、学ぶことで、より効率よく学ぶことができる。
また、NバックトレーニングをするとIQが、上がると紹介されています。
初めて聞きました!
何でも、アプリがあるようです。
Dual N-Back(Android、iPhone) をお勧めされています。(週5日、40日推奨らしいです。)
恐れない

同じ細胞でも、筋肉になったり、骨になったりと違うものが形成されるようです。
同様に、感情によって、ドーパミンが出たり、ストレスホルモンができたりします。
つまり、常にどのような精神状態であるかで、体にいいホルモンがでるか、成長を止めるホルモンが出るか決まるのです。
恐れは、ストレスホルモンを生産します。
起業家のジア・ジアンさん は、恐れを克服するために、1日1回 100日間「ノー」と言われる挑戦をしたようです。
動画は、こちら。
見知らぬ人の家のドアを叩いて、サッカーにさそったり、お金を下さいと頼んだり。。
面白いのは、思ったよりはるかに 多く 「イエス」と言われたことだったようです。
無理難題に対して、どうにかしようとしてくれる人の優しさを感じるとともに、「ノー」と考えていたのは、まず、自分だと悟ったようです。
そもそも、恐れは、古代から引き継がれた感情で、生き残るための本能で、猛獣などを警戒しなくてはいけない状況で、有効に働くものだ。 と説かれています。
恐れは、喜びに変えれれば、良さそうです!
恐れを楽しむ?と効果的ではないでしょうか?

固定概念を振り払って、前向きに考えたい!
体を労わる

パフォーマンスを上げるには、休息も必要です。
日々の生活に楽しみを加えることも有効で、喜びを与えてくれないものを減らし、与えてくれるものを増やしましょう!
著者自身も時間を確保して、自分のための時間を確保しているようです。
著者は、ストレッチしながら瞑想したり、運動したり、散歩しながら太陽光を浴びているようです。
皆さん、喜びを与えてくれるものは、なんでしょうか?
僕の場合は、ショッピング、お酒、食事、小説、映画、旅行とかです^^
休息の取り方にもコツがありそうです。
25分何かを続けたら、5分休むというメソッドが紹介されています。
いつくもの会社で導入したところ、欠勤が減り、生産性、職務満足度、パフォーマンスが高まったようです。

しっかり、休みましょう!
以前、読んだ、モーニングメソッドも本書で、紹介されていました。
ご参考にどうぞ!

運動しましょう!

週3回ランニングしている人の80%は、年間を通して、どこか怪我をしているようです。
その原因は、フォームのようです。
走る、泳ぐ、踊る いずれにしても 正しい、フォームを意識しましょう!
また、座り過ぎが、よくないとのこと。
1日に6~8時間座ったら、1~2時間の運動が帳消しになるようです;;
パーキンソン病の患者に、どのような運動が有益か を調べた結果、ストレッチとウエイト・トレーニングの組み合わせが、最高に効果が表れました。
逆に、長時間のジョギング、自転車などの有酸素運動は、症状を悪化させる可能性があるようです。
有酸素運動は、酸化物質が増えるため、脳や心臓、消化器などに炎症を起こすからです。
筋力トレーニングでも、酸化物質が増えるようですが、他のホルモンの放出で相殺されるのです。
有酸素運動しても筋トレをするとバランスがよくなるので、お勧めされています。

筋トレ しましょう!
持久力をあげるには、低強度の運動で体をたくさん動かし、ときどきウエイト・トレーニングをして、週一回 全速力で走るとよいようです。
お勧めされているレシピは、こちら。
・週一回のウエイト・トレーニング
・週二回のストレッチ
・週一回、全速力で走る
・週に3~6回、20分~60分のウォーキング
ヨガについての記述もありました。
ヨガは、経験がないですが、感情のコントロールにも効果があるようです。
ヨガのメリットを3つ紹介されています。
・背骨が健康になり、全身に影響する。
・内臓をデトックスして、集中力を高めてくれる。
・関節と筋肉に柔軟性をもてる。

ヨガやってみようかなぁ??
食事に気を付けましましょう!

本書で、インタビューした3/4の方が、成果を上げるために最も重要なことは、何を食べるか(食べないか)と言っていたそうです。
昔ながらの食事は、なかなか健康的で良かったそうですが、近代化と共に、不健康になってると提唱されています。
昔ながらの健康的な食事方法
・間食を避けて、お腹いっぱい食べない。
本当の空腹を見極めて、必要な時に食べましょう。
・タンパク質をとる。
乳製品、牛肉、鶏肉、豚肉、魚介類、ナッツなど、筋肉に効果的なタンパク質を取りましょう。
・野菜を食べる。
ポリフェノールが豊富なブルーベリー、ブドウ、緑黄色野菜、(ダークチョコレート、コーヒー)を摂取しましょう!
ポリフェノールが、脳や内蔵で炎症の原因になるフリーラジカルをやっつけてくれます。
・よい油をとる。
植物油(大豆油、コーン油、キャノーラ油)は、オメガ6の主要源で、炎症性の病気(肥満、糖尿病、心臓病、がん、アルツハイマー)の原因となるようです。
バター、アボガド 、ココナッツオイル、MCTオイル、ブレイン・オクタン・オイルが、勧められてます。
MCTオイルを初めて知りました。
聞いたことない方、効果に興味ある方、こちらもどうぞ ↓

腸内の細菌によって、太りやすくなったり、太りにくくなったり、また、疲れやすくなったり、疲れにくくなります。
腸内細菌を元気にするために、プレバイオティック繊維 が望ましいようで、タマネギ、ニンニク、ネギ、アスパラガスに多く含まれています。
過去の記事もご参考ください。腸 いい話! 読みました。

発酵食品も腸内細菌によいです。キムチ、ヨーグルト食べましょう!
本来、虫歯は食事で治せる と聞いたことがあるでしょうか?
僕は、ありませんでした。
子供のころから、虫歯は、なったら治らないと聞いてました。
カルシウムが、適切な箇所にうまく配布されれば、治るというのです!
その役割を担っているのが、ビタミンK2で、歯や骨の健康だけでなく、心臓の健康にも有効とのことです。
ビタミンK2 含め、不足しがちな栄養は、サプリで補うことも推奨されています。
糖質制限についても整理してみました。
ご参考ください。
幸せとは

持っていないものを追求することによって得る「条件付き幸福」は、真の幸福ではない。
幸せになりたければ、いまあるもの、いま置かれている状況に満足しなくてはならない。
なるほど、僕は、もう幸せなはずですね^^
確かに、欲に限りはないので、目標を持って、何かを求めていても、足りないことが少しあっても、幸福感は、持ち続けたいと思いました。
プリンストン大学が、行った研究によれば、7万5千ドルを超えると幸せを感じやすくなるようです。
さらに、興味深いことに、それ以上増えても、幸福感は変わらなくなるようです。
幸せな人は、生産性が 31% 高いという調査結果も出ているようです。
お金を追い求めるのを控え、幸福な環境を求めると、生産性も上がり、自然とお金もついてくるという理論です。
この理論で、成果をあげるには、「最終目標」にフォーカスするとよいようです。
最終目標には、3種類あります。
1.経験したいこと
2.人間として成長したいこと
3.世界に貢献したいこと、あるいは自分の足跡を残したいこと
物は、多く所有すれば、幸せになると考えられそうですが、逆のチャレンジをした方がいます。
毎日1つずつ30日間、モノを捨て続けたそうです。
チャレンジのおかげで、モノの大切さを再考できたようです。
この方は、最終的に、家も捨てて(手放して)、バック2つで生活するようになったようです^^;

僕も断捨離してみました!
ポジティブに!

「最も長く一緒に過ごす5人」の平均が、あなたという人間だ。注意深くその人たちを選ぼう。
5000人を対象にして、行われた調査で、幸せは、3次(友達の友達の友達など)まで広がることが、わかったそうです。
幸せな人に囲まれている人は、幸せになる可能性が高いのです!
皆さんは、どのような人と過ごしてますか?
人間的な深みがあって創造的刺激を与えてくれる人に、いつも囲まれていたら、人生は、磨かれていきます。
ともに時間を過ごす相手を選ぶことは大切だ と提唱されています。
一緒にいる人たちが、最高のあなたを引き出してくれるのか、引きずり降ろそうとしているのか、注意しましょう。
そして、限界を超えるよう刺激してくれる人の近くにいましょう^^
また、頭の中に飛び交う批判の声が、持てる能力を制限してしまうので、瞑想で「正しい声」を響かせよう と言われています。
2章を使って、瞑想に触れています。
瞑想のメリット
・ストレスが減る
・不快感が消え、その感情に適切に対処できる
・自分にも他人にも優しくできる
・左右の脳のつながりが大きくなり、集中力が増す
瞑想には、いろいろあるようで、自分にあったものを探せばいいそうです。
最初の1カ月、毎日5分行うことを勧められています。

Youtube で、瞑想どんな感じか、みてみます!
最終的に、幸福感には、感謝の気持ちが大事で、著者の成功するために大事な3つのことの中で、最初に「感謝」をあげられています。
インタビューした多くの人たちも、感謝がなければ、成功も幸福もなかった と語ったそうです。
著者は、家が有毒なカビだらけだったこと、大金を失ったことにも感謝しています^^;
感謝しているときは、神経系が安全を告げるため、リラックスできるようです。
(寝る前に感謝すると、疲労回復効果も上がるようです。)
また、全てのことに感謝するには、赦すという ことも重要です。
その際に、「まぁしょうがないから 赦す」では、自分が納得してないので、効果がないそうです。
嫌なヤツにさえ感謝と同情の気持ちを抱ければ、相手の行動にエネルギーを奪われることはなくなる。幸福もアップする。
イライラするときは、ネガティブなストーリを自分でつくってるので、ポジティブなストーリに書き換えましょう!
感謝を習慣化するために、いくつか方法を紹介しています。
・感謝日記をつける
・感謝できるチャンスを探す
・感謝をシェアする
・感謝の手紙を書く
本書も最後は、謝辞で締められています。
感謝することがパフォーマンスの向上と幸福にとっていかに大切かを知っている。だからといって、このセクションを書くのが簡単というわけではない。ぼくはあまりに多くの人々に感謝しているからだ。
感想

課題というか、取り込める部分の多い一冊でした!
全てのライフハックが、専門家のインタビューから得られているので、とても説得力がありました。
また、ストーリーを交えて、効果などを説明しているので、とても読みやすかったです^^
僕自身は、本書を読んで、下記のようなことに、挑戦していきたいと思いました。
・イライラした時に、原因は何かを考えようと思いました。
そして、イライラする代わりに、もっといいアプローチがないか考えてみます。
・楽しい仕事に比重を置いて、消耗するものを避けるか、楽しめるように工夫していきたいと思います!
・Dual N-Back(アプリ) をやってみました。
なかなか、難しい。。続けてやってみたいと思います。
・ジョギングを見直して、週間トレーニングを再度考えてみます。
具体的には、筋トレを増やして、全速力で走る日を設けたいと思います。
・フライドポテト、唐揚げなど、揚げ物を避けようと思います。
・ビタミンK2のサプリを飲んでみます。
・最終目標を考えます。
・捨てられるモノがないか、考えようと思いました。
・感謝しまくります。(日記も書こうかな)

最後まで、ご覧いただき、感謝します!







コメント